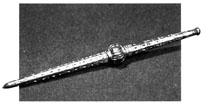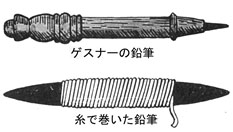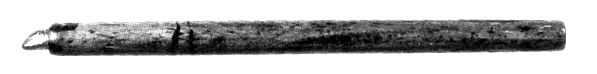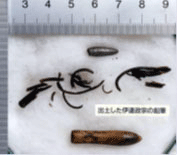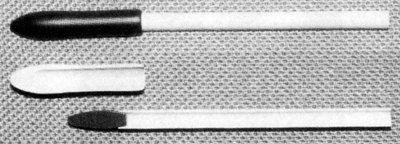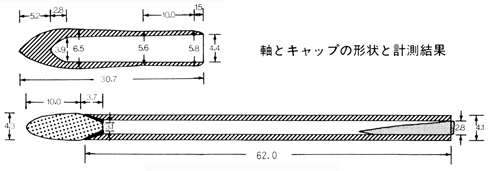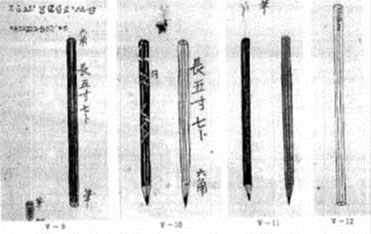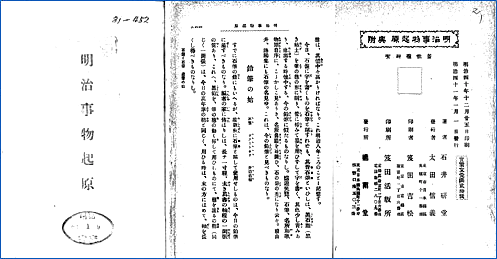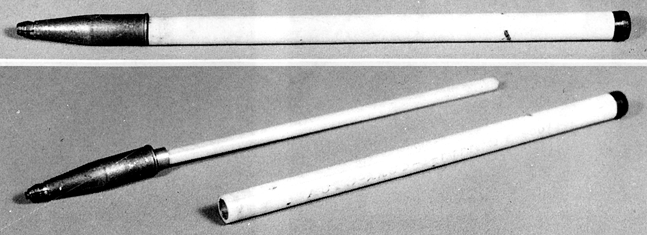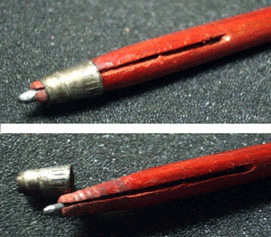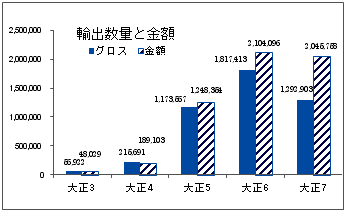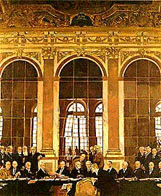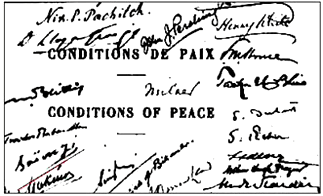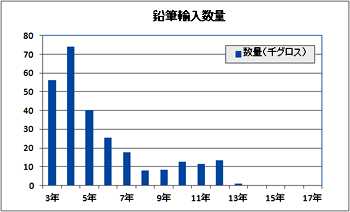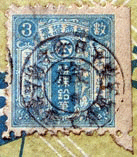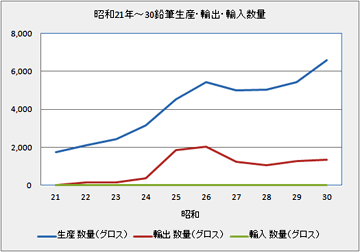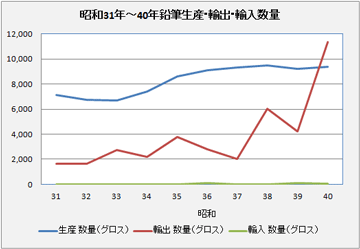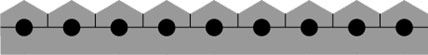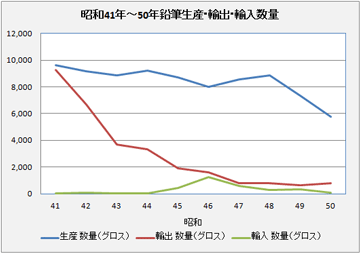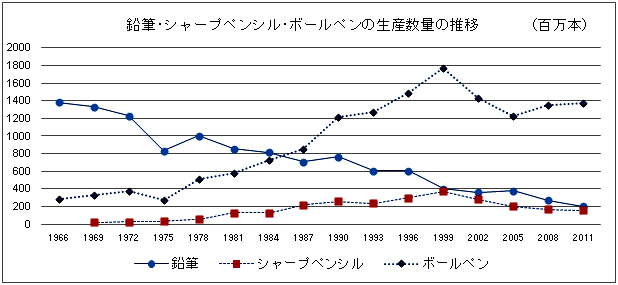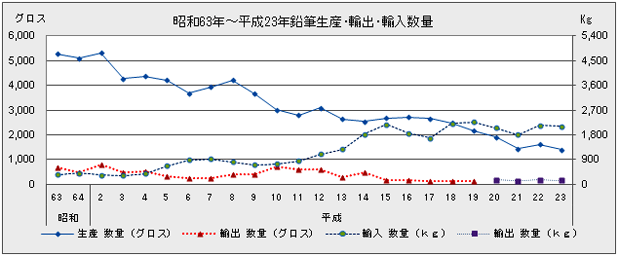|
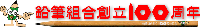 |
|
| |
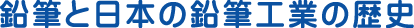 |
|
|
|
|
|
| ■ 鉛筆の起源
|
| ■ 明治の鉛筆の歴史
|
| ■ 大正の鉛筆の歴史
|
| ■ 昭和の鉛筆の歴史
|
| ■ 平成の鉛筆の歴史
|
|
|
|
- TOPに戻る - |
|
| |
|
|
|
| 鉛筆の起源 |
鉛筆の起源については、正確な文献が少ないので、原書から要約する程度であるが、筆記用具として広く用いられるようになったのは、比較的近世のことである。文字の発明は遠く7,000年以前からであると伝えられ、メソポタミア地方の楔形文字も粘土板の面に鋭利な器具をもって掘り込まれ、ナイル川流域のエジプト文字は、植物の汁をもって、パピルス紙にしるされ、バビロニアでは、羊皮紙に記録したといわれているが、文化が進むにつれて文字の発達があり、文字を記録するための筆記用具が考案発明されて、今日に至ったのである。
古代ギリシャ・ローマ時代になると、人びとはすでに鉛筆に似た道具を持っていたことが知られている。
もっとも、当時は、先のとがった鉛筆は貴重な紙を損うと考えられていたから、似ているとはいえ、まだまだ現在の鉛筆とはほど遠いものだったにちがいない。
ことに、製図用としては、丸い小さな鉛の円板が好んで用いられた。ローマ人は「プレダクタル」、ギリシャ人は「パラグラフォス」とこれを呼んでいたことがわかっており、その痕跡は、古い羊皮紙の上に、今日なお見ることができる。
ようやく14世紀になって、現在、私たちが使用している鉛筆と似たものができたらしい。有名なオランダの画家ヤソファソオイックは、鉛筆ふうの道具で製図したと伝えられているが、同じころイタリアでも、現在残っているミケランジェロのスケッチ画などから、鉛と錫(すず)を混ぜて芯にした鉛筆があったことがわかる。この鉛筆は、シルバー・ポイント「銀筆」と名づけられ、ルネッサンス期の画家ばかりでなく、筆記用としても用いられた。 |
|
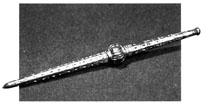 |
1565年頃のイギリス人、グッナーの著書に、鉛筆の説明が出ているが、これは鉛筆に関する文献として最も古いものであろう。
グッナーは、その著書の中で「製図および筆記の目的には、鉛または人工的混和物より成るシンに木製の握りを付し、鉛色の光沢ある物質として用いたが、この物は脂肪のような手ざわりで、指に色がつくので粘土を混ぜて耐火質の物として用いるようにした云々」と書いてあるが、イタリア人イムベラーはこの物を「グラフイヲピンビノウ」と名づけた。これはグッナーの時代に、イギリスで発見された物で、今日の鉛筆のシンの原料となるグラファイト(黒鉛)にあたるのである
|
|
|
| シルバー・ポイント(銀筆) |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
世界の鉛筆の始まり(イギリス、ボローデール渓谷でグラファイト発見) |
|
|
| 1564年、エリザベス女王時代に、イギリスのカンバーランド山脈、ボローデール渓谷(スコットランドに境を接するイングランドの北部地方)で、羊飼いが倒木の根の穴から偶然黒鉛の結晶を発見した。人びとは、はじめ、その重要性を認識できなかったが、やがて、黒くなめらかな性質に着目し、これを筆記道具に用いることを思いつくと、黒鉛の塊を細く切ったり、握りの部分を紐で巻いたりして使いはじめるようになる。 |
このことが刺激となって1565年に、イギリスで最初の鉛筆製造が始まった。もっとも、近代のような製法ではなく、坑内から掘り出された黒鉛を精選し、これを板状、または棒状にして板にはめ込むという簡単なものに過ぎなかった。1565年頃ドイツ系スイス人で博物学者コンラート・ゲスナーは、木や金属でできた丸い筒状の先端に黒鉛の小さな塊を詰めたものを筆記具として使っていた。
人びとにとって、この鉛筆がどれほど珍しく、また貴重なものであったかは、想像に難くない。飾りのついた美しい“さや”が作られたりしたことなども、この鉛筆が単なる筆記道具としてよりも、むしろ貴重品として扱われていたことを物語っている。 |
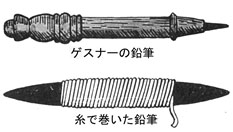 |
| 1565年頃の鉛筆 |
このように、黒鉛が鉛筆の芯としてにわかに注目されるようになると、乱掘をおそれた英国政府は、特別保護法を定めて、採掘期間を年にわずか6週間と限った。採り出された黒鉛はロンドンの公設市場に運ばれ、毎月第一月曜日に競売されたが、その輸送には軍隊の護衛がつくほどであった。黒鉛の海外輸出も法律で禁止され、製品だけが海外の鉛筆市場を独占した。
しかし、このような保護がなされたにもかかわらず、17世紀になるとボローデール鉱山は衰弱し、もはや、純粋な黒鉛を採掘することは不可能になった。このため、あちこちで探鉱が試みられたが、結局、ボローデール産にかわるような良質の黒鉛は発見されず、当然のなりゆきとして、英国の鉛筆製造業者は、これまで使っていた黒鉛の層を、なんらかの方法で加工し、鉛筆の芯に用いなければならなくなった。
さまざまな方法が試みられたあげく、黒鉛と硫黄を混ぜこれを溶解して芯をつくる方法がいちばん良さそうだ、ということになったが、やはり以前の純粋な黒鉛に比較すると格段の差があった。しかし、ほかにいい製法も発明されないまま、これが長い間使用された。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
| |
ドイツの鉛筆 |
|
|
ドイツでは、すでに16世紀から黒鉛の粉末に硫黄を混合する技術を持ち、品質では英国の鉛筆をしのいでいた、といわれている。そして、1760年には、今日、世界で最も有名な鉛筆会社の一つであるA.W.ファーバー会社の先祖カスパー・ファーバーが、ニュールンベルグ近郊のシュタイン村に工場を建設し、翌年から鉛筆製造を開始した。
ドイツの鉛筆工業は、英国製鉛筆に圧倒されて市場が限定され、その発展には非常な困難が伴ったが、政府の鉛筆工業奨励やその後フランスで発明された新しい製法の採用などで品質向上、設備の改善につとめた結果、やがてババリア鉛筆として世界に進出することになる。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
フランスの鉛筆(コンテによる発明、現在の鉛筆芯製法の基礎) |
|
|
1795年にフランス人フランス政府科学部門の学者N.J.コンテによって、黒鉛と粘土を混合して、それを高温で焼きかためて鉛筆をつくることが発明された。これが、現在の鉛筆芯製法の基礎となった発明である。
コンテの鉛筆芯は、単に焼きかためる工夫をしただけでなく、黒鉛と粘土の混合割合を変えることによって、芯の濃度が変化することも発見した。
後にこの製法は、各国にもたらされ、ここに初めて近代的な鉛筆工業が誕生することになったのである。 |
|
| ナポレオン皇帝と鉛筆 |
|
| フランスが鉛筆製造を真剣に考えるようになったのは18世紀末、イギリスおよびその連合軍との戦争で鉛筆の輸入が途絶え、その結果、戦争も、教育も、日々の生活にも鉛筆の重要性が認識された。ナポレオンは当時39歳であった画家で、気球の研究もしていた科学者のニコラ・ジャック・コンテに研究を命じ、1794年頃完成させ1795年に特許を取得している。 |
 |
| 板でサンドイッチした鉛筆の原型(レプリカ) |
|
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
アメリカの鉛筆 |
|
|
19世紀の中ごろ、新大陸アメリカ東海岸に移住したドイツの鉛筆業者が、鉛筆の製造を始めた。アメリカで最初の鉛筆が製造されたのは、南北戦争が起きるちょうど10年前、1851年のことだが、以来、天与の資源−良質の軸材として最適なシダーを産出するだけでなく、メキシコで良質の黒鉛を得て、国力のめざましい発展とともに成長し、鷲印鉛筆として知られているイーグル・ペンシルや、アメリカン・ペンシル・カンパニーという工場ができた。現在は中国にその地位を譲ったが、一時、アメリカは世界第一の生産を誇る鉛筆工業国であった。
なお、レッドシダーにかわって開発されたカリフォルニア産インセンスシダーは、まるで鉛筆のために生まれてきた木とまでいわれ、今日まで主要な軸材となっている。
鉛筆の製造はイギリスに始まり、ドイツ、フランス、アメリカと各国が工業化に努力し、今日に至ったのである。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
日本の鉛筆の始まり
徳川時代の初期、はじめて鉛筆が渡来、徳川家康に献上された |
|
|
| わが国にはじめて鉛筆が渡来したのは徳川時代の初期、オランダ人によって徳川家に献上されたと伝えられている。現在、静岡県の「久能山東照宮博物館」に徳川家康公の遺品として保存されているのが、現存する日本最古の鉛筆である。 |
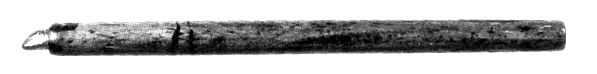 |
| 徳川家康 所用の鉛筆 久能山東照宮蔵 |
|
| 徳川家康の遺品 |
博物館の説明文には『記録がないので渡来の経路は不明。現在、日本で鉛筆の芯に用いている黒鉛はメキシコ、マダガスカル、セイロンなどの産で、メキシコ産が最も良質であるが、鉛筆の芯を電子顕微鏡で調べたところによると、メキシコ産の純黒鉛(石墨)である。おそらく、スペインあるいはその属領であったメキシコかフィリピンから家康在世中に渡来したものであろう。
黒鉛を鉛筆の芯に使用したのは16世紀半ば(家康の青年期以降)とのことで、この鉛筆はもちろん日本に現存する最古の鉛筆である。「軸木の長さ11.4cm、X線撮影により芯の長さが6cm、2ヵ所にヒビが入っているのが判明している」とある。
ついでにいえば、徳川家康のお手廻り品のなかには、この鉛筆ばかりでなく舶来の枕時計や眼鏡、ガラスの薬瓶などがあって、家康が新しい文化を実生活にとり入れた先駆者であったことが知られる。
一方、赤色鉛筆では、明治以前にわが国に渡来し、現在も残っているというものはない。ただ、姫路市の姫路神社に「赤色鉛筆で書いたのではないか、と思われる奉書紙の文書が保存されている」と長い間いわれてきた。この文書は徳川幕府の大老で徳川家綱に仕えた酒井忠清の覚え書きの一部だと伝えられていたが、どういう事情か、現在は見当たらないそうである。だが、これから察するに赤色鉛筆も、少なくともこの時代には日本にもたらされていた、と見ていいだろう。 |
|
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
伊達政宗の鉛筆「仙台博物館の調査研究報告」により、平成元年3月に明らかにされた |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伊達政宗の鉛筆 |
政宗の鉛筆は家康のものと形状は全く違って筆状のものであった。
昭和49年に国宝の伊達政宗の墓所、瑞鳳殿に調査が行われ、その後の細かな調査の中で鉛筆が発見された。
発掘された鉛筆は、長さ62mm、直径4mmの木の軸の先端に長さ13mm、径4mmの芯をはめ込んだものである。鉛筆自体の長さは約74mmであるが、その先端に長さ30mm、径6mmのキャップがかぶせてある。これをさらに長さ128mm、径10mmの木簡に収めてあった。
こうして発見された正宗の鉛筆であったが、その後の劣化により、その当時の形状をとどめていない。(昭和63年に復元された)
家康は正宗より20年早く元和2年(1616)に死亡しているので当然家康使用のものが正宗使用より古いと考えられるが、鉛筆の型式から考えると正宗使用のほうが古い型をつたえている。 |
| (日本鉛筆史掲載・仙台市博物館調査報告書) |
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
幕末に渡来した鉛筆 |
|
|
ペリー提督が浦賀に来航した嘉永6年(1853)に幕府に献上した品物の中に、当時の日本人にはまだ珍しい鉛筆があったのだが、このときの日本側の資料には、鉛筆についてはごく簡単なスケッチしか残されていないようである。ところが、それから2年後の安政2年(1855)4月25日、仙台に程近い宮城県石巻にブローク船長搭乗の米船が来航し、そのときの様子が「仙台市博物館調査研究報告 第9号」に、学芸員の小井川百合子氏によって克明に調査・記録されている。
当時の仙台藩は外国船来航の報に騒然となったとのことだが、4日後の4月29日に去ってゆくまでの間に、応対した武士たちは船内にも招じ入れられ、ささやかながら日米の交歓があったようである。当時ブローク船長らの応対に当たった千葉寛平が、船長から贈られた初めて目にする鉛筆に関して精緻な図を描いていたのである。 |
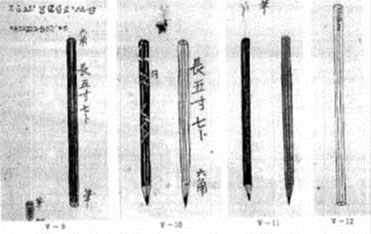 |
千葉寛平が、船長から贈られた鉛筆に関して精緻な図
仙台市博物館蔵 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
日本の鉛筆工業の歴史 |
|
|
わが国による鉛筆づくりは明治時代初期に始まる。
この頃の鉛筆づくりの形態は「手工業」で、「産業」と呼ぶには至っていない。
維新を経て、多くの若者が特使として渡欧し、政治、法律、徴兵制等の近代国家の仕組みを勉強していた際、都市にあったさまざまな西洋文物をわが国に持ち帰った。なかでも鉛筆、石鹸、マッチ等の日常生活用品、つまり、今日でいう中小工業的商品類の製造法に関しては、明治10年代から20年代に、日本と欧州との間に積極的な人材の往来があり、製法の研究・伝授は大いに進んだ。
第1回の内国勧業博覧会の出品区分によれば鉛筆は第16類「教育の巻具」に分類され、明治3年に輸入が始まったばかりで当時まだ物珍しかった鉛筆が、単なる書斎の道具として扱われていたのではなく、近代国家の建設に欠かせぬ教育の機器として扱われていたことは、当時の新政府の関係者の鉛筆に寄せる熱い思いをみて取ることができる。 |
|
| 「明治事物起原」 |
| 明治41年(1908)に発行された「明治事物起原」の「鉛筆製造の始」という章があり、わが国の鉛筆の始まりについての記載がある。わが国に鉛筆を根付かせた手工業時代の代表的な人物の記載がある。 |
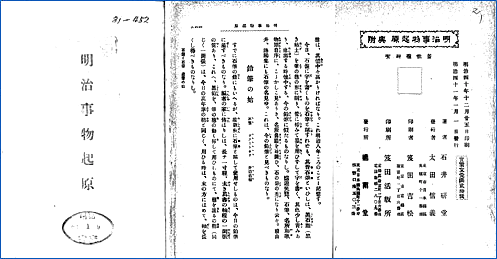 |
|
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
日本で最初に鉛筆づくりを始めた樋渡源吾 |
|
|
| 安政6年に開業した樋渡源吾は、第1回勧業博覧会で鳳紋賞牌を受けた。陸前牡鹿郡産出の鉛色土にゴム糊を混ぜて乾燥し、軸は桂を使用し、芯を乾燥させ、桂の管中に差し入れると記録にある。 |
|
| 初めて鉛筆を作った謎の日本人・仙台の樋渡源吾とはどんな人物か!? |
第1回の内国勧業博覧会に日本で鉛筆を作って出品した人が二人いて、一人は東京の小池卯八郎、もう一人が、何故か仙台の樋渡源吾という人物であった。
仙台の樋渡源吾については謎の多い人物で詳細な情報が伝わっていなかったが、明治10年の内国勧業博覧会の出品記録によれば、「宮城県陸前国宮城郡仙台北二番丁上杉山通」に住居し、創業は小池の明治7年(1874)に対して、何とそれより15年も前の安政6年(1859)と記録に残っている。
安政6年といえば時の大老井伊直弼が尊皇嬢夷を唱える反幕派の弾圧を強行し、吉田松陰など多くの志士が処刑された、いわゆる安政の大獄が吹き荒れた年である。このような時期に、しかも今まで鉛筆の歴史には登場したことのない人物が仙台にいたのである。
源吾は、前述の仙台藩に献上されたアメリカの鉛筆(A.W.ファーバー社製の2Bの鉛筆だった)の詳細を仙台藩で百石取りの兄の道亨(みちとう)から聞き、あるいは手にする機会を得て、源吾が鉛筆というそれまで未知の筆記具の製造を開業したのは米船来航から僅か4年後の安政6年、源吾34歳の時のことである。
明治10年の博覧会出品に当って源吾が事務局に提出した鉛筆の芯の製造法を見ると、下記のように説明している。
「製法 鉛色土・管下陸前国牡鹿郡小横浜民有地ノ産・ヲ護謨糊ニ混和シ鉄製ノ飽機(ツキダシ)ヲ以テ撞キ起シテ細線トナシ之ヲ晴日ニ乾燥セシメテ後 種木ノ管中ニ刺入ル者ナリ」・・・・・この方法は、小池が博覧会事務局に提出した鉛筆芯の製造方法とよく似ている。二人ともまだ今日の鉛筆芯の製法のもっとも重要な工程、つまり高温で芯を焼結するという手段はとらず、細い芯を押し出して、それを乾かして固めたと述べており、今日の色鉛筆の芯のような製法をとっていたようである。
樋渡源吾は明治23年に上野で開催された第3回の内国勧業博覧会にも鉛筆を出品している。こうして博覧会に最初に出品してからでも13年間鉛筆を作り続けていたのに、名前も現物も残っていないのはなぜだろう。自分で作った芯の大部分は、明治20年代に仙台の連坊小路で鉛筆の製造を志した老舗の筆舗玉光軒などの毛筆屋に卸していただけで、鉛筆としては僅かな量しか完成させていなかったのではなかろうか。 |
| (トンボ鉛筆伊藤眞吉顧問考察) |
|
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
明治6年開催のウィーンの万国博覧会に技術伝習生(藤山種廣、井口直樹)派遣 |
|
|
明治6年(1873)、ウィーンで開催された万国博覧会に、明治新政府は17名の伝習生をヨーロッパに派遣し、そのうちの一人として渡欧した藤山種廣、井口直樹がウィーンから鉛筆製法を伝えた。
井口はドイツ・ヒットワイス鉛筆製作所の製造機械の図解を模写、さらに黒鉛を携えて帰国した。藤山は、万博で好評を博していたボヘミア(チェコ)のハルトムート氏の鉛筆の製造所(現在のコイノールリ/ルトムート社)で「黒鉛と薬品の交合」を研究分野として研修に努め、帰国後、士族の小池卯八郎にその技術を伝えた。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
明治10年の第1回内国勧業博覧会に小池卯八郎国産初の鉛筆を出品 |
|
|
日本の公衆が鉛筆という便利な筆記具を目にする機会があったことを証明する最初の正式な記録は、明治10年(1877)8月21日に上野で開催された第1回内国勧業博覧会の時である。
この博覧会は、明治新政府の中枢にあって「富国強兵・殖産興業」こそが、近代化を目指す日本にとって欠かせぬ課題と認識していた内務卿・大久保利通が、その達成のためのもっとも効果的な施策として、海外で開催されていた万国博覧会を参考に102日間にわたって開催したもの。開会式には明治天皇も出席され、期間中の総入場者は45万人に達したという。
ちなみに、この年3月には西郷隆盛率いる反政府反乱軍鎮圧のため熊本に向った政府軍が田原坂の激戦に勝利し、更に博覧会会期中の9月24日には西郷が鹿児島の城山で自刃するという、物情騒然たる中での強行開催となったのである。
小池は、この第1回内国勧業博覧会に国産初の鉛筆を出品した。
小池は下広徳寺(銀座との説もある)に小池鉛筆製造所を明治7年(1874)に開設して鉛筆の製造を開始したとのことである。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
明治13、14年頃 河原徳右衛門、小石川第六天に工場興す、多くの鉛筆職人を輩出 |
|
|
神奈川県金沢出身の河原徳右衛門(不詳−1888)は、誰に学ぶともなく苦心して黒芯鉛筆を製造、明治13、14年頃に小石川第六天に工場をもち、100人近い職工を使った。そして14年開催の内国勧業博覧会で二等賞を受けた。明治15年、河原は事業に失敗するが、杉江鉦三郎など多くの鉛筆職人を輩出した。
杉江鉦三郎は、明治17年(1884)下谷区竹町に杉江蜻蛉社設立、明治26年杉江蜻蛉社に入社した鉦三郎の義兄小川作太郎は、その後明治31年頃独立して下谷根岸に工場を設立。 |
|
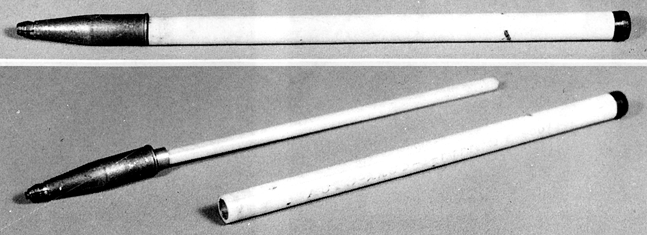 |
| 河原徳右衛門と上條幸助が製作した明治初期の鉛筆 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
明治20年(1887)眞崎仁六、眞崎鉛筆製造所を内藤新宿1番地に興す |
|
|
眞崎仁六(1848−1925)について、明治事物起源には「鉛筆製造界に一異彩あるは眞崎鉛筆製造所なり。誰にも師事する所なく自案の考案に成る機械方法を使用し・・・・・螺旋口金物にて芯を抑える式(固定)の鉛筆特許権を有せり」と記載されている。
明治11年(1878)のパリ万国博覧会の一隅に展示された各種の鉛筆が、それからの眞崎仁六の一生を、決定的に運命づけることになった。
パリから帰国するや、眞崎仁六は研究を開始したが、パリから持ち帰った鉛筆の知識はといえば、わずかに「鉛筆の芯は黒鉛と粘土の混合物らしい」ということだけである。それだけに、研究は非常な困難を極めた。良質の粘土と黒鉛の入手を解決すべきだったが、国内にそれを求めるのは容易ではなかった。
鹿児島県加世田の黒鉛、栃木県烏山の粘土が、鉛筆の芯として、軸材は北海道産のアララギが望み得る最高の品質であることを突きとめた。芯に5年、軸と機械に5年、10年間の研究により眞崎鉛筆製造所の設立となった。 |
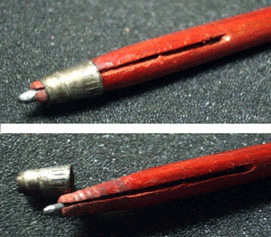 |
眞崎仁六が創業当時製作されたとされる
「はさみ鉛筆」 |
| 眞崎仁六の眞崎鉛筆製造所が現在の三菱鉛筆株式会社に、また河原徳右衛門の門下生の杉江鉦三郎と共に鉛筆づくりを始めた小川作太郎が、現在の株式会社トンボ鉛筆に、それぞれ発展している。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
明治時代の鉛筆業界 |
|
|
鉛筆が文房具としてわが国に輸入されたのは、明治10年(1877)頃といわれているが、公式には明治18年(1885)、輸入品目に鉛筆が指定されたのが最初である。したがって、それ以前の輸入はおそらく見本程度の数量に過ぎず、ようやくこのころから、鉛筆が商品として扱われるようになったものであろう。
また、公立小学校上級生に英語の授業が行われるようになり、鉛筆の需要は急速に高まった。
当時の輸入鉛筆にはイースタン・レッドシダーが使われていた。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
明治の終わりには鉛筆製造業者が40軒余、明治45年(1912)「東京鉛筆製造組合」が創設 |
|
|
鉛筆製造業者は、明治時代にはすでに40軒余りが記録(日本鉛筆史参照)に残されおり、大正時代になると鉛筆製造業は急速に「工業化」していった。
鉱工業の発展、教育の普及、通信の要求等のいわゆる近代化が図られたため、特に首都圏(当時東京市)で鉛筆の需要が確実に高まっていった。
大正初期、「国産鉛筆が6割を占め、残る4割が米独の輸入品だった」と「教育文化用品工業便覧(昭和25年(1950)発行)」が伝えるほど、わが国の鉛筆製造業は質量ともに充実してきた。
明治45年(1912)、鉛筆の改良発展を目的に準則組合法に基づき「東京鉛筆製造組合」が設立された。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
大正3年第1次世界大戦勃発、わが国に注文殺到 |
|
|
東京鉛筆製造組合が創設されて2年目の大正3年(1914)に、第1次世界大戦が勃発した。この大戦による世界的なドイツ製品封鎖が日本の鉛筆産業を“工業”へと大きく躍進させた。
ドイツは最も早く鉛筆生産を工業化した国で、ドイツの工業鉛筆は一世を風靡していた。当時、「アンデス山脈の頂にもCASTEL鉛筆が行きわたっている」と形容されたほどだった。
このドイツ鉛筆が全世界からシャットアウトされることになって、わが国の鉛筆生産者も世界のマーケットの空白を満たすために量産化が急がれた。
|
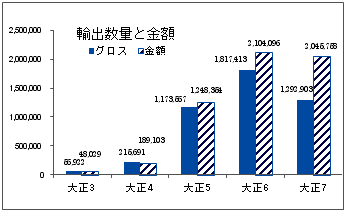 |
| この第1次大戦を契機とする未曾有の好況が、日本の鉛筆産業を「鉛筆工業」に変えた始まりであり、生産は機械化され、先進国の生産設備が輸入され、生産・販売量に伴って流通も整っていった。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
粗悪品が国際信用落とす、「日本輸出鉛筆同業組合連合会」設立、輸出鉛筆の自主検査実施 |
|
|
軽工業品にはよくあることだったが、品不足に乗じて粗悪な鉛筆をつくる者もあり、特に鉛筆の中程に芯の入っていないキセル鉛筆等も現れ、「日本の鉛筆は安かろう、悪かろう」と国際信用を著しく落とす事件も発生した。
これを防ぐべく大正7年(1918)10月、重要物産同業組合法に基づき、東京と大阪に鉛筆同業組合を設立し、自主検査を行うことになった。
さらに翌大正8年1月、「日本輸出鉛筆同業組合連合会」を設立し、農商務省令「輸出鉛筆等取締規制」に基づく輸出検査が義務付けられた。
同法による義務は大正7年から昭和2年(1927)まで続いた。
昭和2年には、重要輸出品工業組合法による日本輸出鉛筆工業組合連合会が設立され、輸出検査を継承した。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
ヴェルサイユの講和条約に日本製鉛筆が採用される |
|
|
第1次世界大戦は鉛筆の有力生産国としての「日本」を世界に認知させる結果となった。
大正8年1月(1919)、パリのヴェルサイユ宮殿で講和会議が開催され、ドイツとの間に講和条約が締結され大戦は終結したが、この講和会議で用意された鉛筆はすべて「Made in Japan」だったと語り継がれている。 |
|
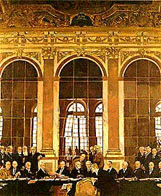 |
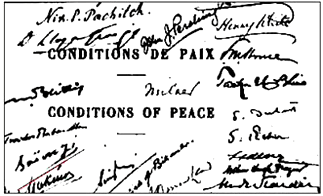 |
『ヴェルサイユ宮殿、鏡の間における
講和条約調印、1913年』
作ウイリアム・オルペン |
『ヴェルサイユ条約(平和についての条件)』の表紙 |
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
鉛筆輸入が激減 |
|
|
昭和5年(1930)に産業合理化政策が公布された。同政策は官公庁と軍等の公的機関がその物品調達において、「国産品にて支障なき限り、外国品を避け、国産品を見積もること」と取り決めた。
機敏に対応した業界は、3種の鉛筆を「優良鉛筆として選定」させた。
こうしてキャステル、ステッドラー、アポロなどの当時一級品とされていた外国品をすっかり国産品に置き換えることができ、保護貿易政策の流れに乗って国の調達品を大転換させ、以降、鉛筆輸入は激減していった。 |
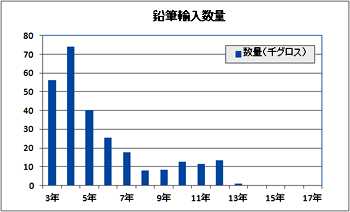 |
| それ以上に、関東大震災(大正12年9月1日)で壊滅的打撃を受けたにもかかわらず、鉛筆業者は先進国に伍する品質向上に努めていて、その品質という力をもって政策をテコに国産主流の流れをつくることができた。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
日米鉛筆貿易摩擦が発生 |
|
|
昭和一桁時代の生産数量500万グロス台の約半数が輸出であった。
大正3年を皮切りにわが国に突如舞い込んだ大戦特需のピークが大正6年の182万グロスだったので、昭和一桁時代における輸出向け250万グロス生産体制は驚くべき発展であった。
わが国の鉛筆産業の強力な国際競争力と輸出超過が新たな火種を生むことになった。
当時の米国国内の相場では日本製鉛筆が1セントであったのに対して、ドイツ製鉛筆は5セントで、米国の鉛筆業者は日本製にかなり痛めつけられていた。そこで関税による措置でこれを阻止すべく米鉛筆事業者は政府にロビングを繰り返し、その結果、ルーズベルト大統領は「ニューディール」<昭和8年(1933)〜>の一環として海外製鉛筆を対象に「従量税」と「従価税」の二重の関税を課すことを決めた。
「1セント鉛筆がストップする法律が可決しそうだ」とわが国にこれが伝わると、ワシントン貿易委員会の公聴会に出席して反対意見を述べて欲しいという依頼が組合に舞い込み、商工省、外務省の協力を得て、米人弁護士を代理人として公聴会に出席させることができた。
その結果、輸入禁止という最悪事態は避けられ、年間20万グロスの輸入を12万5千グロスに制限すること、日本国内の自主規制によって粗悪品を追放すること、という協定を日米間でとり結ぶことになった。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
鉛筆の公定価格・丸公価格 |
|
|
 |
昭和14年(1939)10月20日物価「価格等統制令」により、すべての物価は昭和14年9月18日の価格に凍結された。
鉛筆業界における戦時統制の動きも、まず価格の面から始まった。昭和14年(1939)3月には三菱鉛筆(眞崎大和鉛筆)、地球鉛筆(日本鉛筆)、月星鉛筆(市川鉛筆)、トンボ鉛筆、ヨット鉛筆など、いわゆる大手5社の最高標準価格が、各銘柄別に制定された。
|
10月には物価統制令の公布によっていわゆる「9.18価格」が行われ、それ以後、値段は完全に据え置きになる。
翌15年(1940)には、それまで各社の価格表を基礎とした銘柄別の公定価格が決定し、さらに銘柄別から規格品別となって業者全般に当てはまる価格が決定し、630万グロスという歴史的な生産を誇った昭和15年(1940)10月12日、鉛筆の公定価格が制定された。
先だって施行された国家総動員法<昭和13年(1938)>、価格統制令とあわせて物資と労働力に関する軍の介入が強まり、鉛筆も輸出品にかかわらず、国内用鉛筆も検査合格品でなければ公定価格で販売できなくなった。
こうして価格は実質的に凍結された。この結果、業者は公定価格を維持するため一斉に品質の向上に努めたので、業界の秩序が保たれたばかりでなく、消費者にもメリットをもたらすことができた。このように、鉛筆の公定価格は、国家の戦時統制ではあったが、一面、業界の安定と品質向上にも役立ったのであった。 |
|
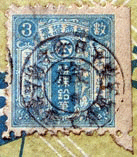 |
鉛筆の箱に貼ってあった「日本輸出鉛筆工業組合聯合会」の証紙 |
|
| |
| 鉛筆統制額告示一覧表 |
| 小売1本統制額単位:円 |
| 種類告 示年月日 |
15.10.12 |
20.6.5 |
21.2.20 |
21.9.21 |
22.7.2 |
22.10.25 |
23.10.29 |
| 学習用 |
0.05 |
0.10 |
0.25 |
040 |
1.00 |
2.00 |
3.90 |
| 事務用 |
0.05 |
0.10 |
0.40 |
0.60 |
1.50 |
2.30 |
4.00 |
| 製図用 |
0.15 |
0.20 |
0.50 |
0.80 |
2.00 |
3.20 |
5.00 |
| 色鉛筆 |
0.15 |
0.20 |
0.70 |
1.30 |
3.00 |
6.00 |
9.50 |
| 手帳用 |
0.05 |
0.10 |
0.30 |
0.40 |
1.00 |
2.50 |
4.00 |
| 手帳コッピー |
0.10 |
0.15 |
0.50 |
1.50 |
2.50 |
4.50 |
7.00 |
| 図画用 |
0.10 |
0.15 |
0.50 |
1.50 |
2.50 |
4.00 |
6.50 |
| 写真修正用 |
0.30 |
0.30 |
0.80 |
2.00 |
3.00 |
4.80 |
7.50 |
| 硝子、皮膚用 |
0.20 |
0.25 |
1.00 |
2.50 |
4.40 |
8.50 |
13.50 |
| 黒紫コッピー |
0.15 |
0.20 |
1.00 |
2.50 |
4.30 |
7.30 |
11.50 |
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
昭和19年「日本鉛筆製造統制組合」設立 |
|
|
昭和19年7月、工業組合法が廃止され東京・大阪の鉛筆工業組合並びに日本輸出鉛筆工業組合連合会を解散し、「日本鉛筆製造統制組合」が設立された。
自主的な工業組合時代の組合員であった業者も、その企業形態(工程別)の制約を受けて統制組合に加入出来なくなったのである。統制組合は、木工、塗り、仕上げの3工程以上を営む者が加盟資格になっており、他の業者は下請業者となった。
また、組合は地区別に指定を受けた。
国と軍の強権の下にありながらも、わが国が国力をアジアに顕示したこの時代、鉛筆はわが国の文化文明の代表的「宣撫品」として選ばれ、広く供給された。
統制組合は戦後、昭和22年(1947)2月の同法廃止まで続き、以降、今日に至る「東京鉛筆工業協同組合」として再出発した。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
昭和20年の敗戦、壊滅的打撃、同年生産は89万グロスに落ち込む |
|
|
第2次世界大戦により、東京地区に7割の事業者と工場が集中していた鉛筆産業にとって、焼夷弾による空襲は壊滅的な打撃をもたらし、昭和20年(1945)の生産は89万グロスにまで落ち込んだと雑貨統計に記録されている。
昭和20年(1945)の日本鉛筆製造統制組合事業報告書は「本年度来(20年度)現在に於いて戦災により組合員の店舗、工場の羅災したる組合員数23名.」と記録している。
統制組合時代は昭和19年7月から終戦を経て、昭和22年2月の組合法廃止まで続いた。
昭和20年12月、鉛筆統制組合の調査による当時の業界の状況は次の通りであった。 |
|
構 成
| 組合員数 |
41名 |
| 従業員数 |
1,790名 |
| 下請業数 |
51名 |
| アウトサイダー |
2名 |
|
|
地区別組合員数
| 東 京 |
27 |
| 山 形 |
1 |
| 長 野 |
1 |
| 群 馬 |
1 |
| 三 重 |
1 |
| 兵 庫 |
1 |
| 大 阪 |
7 |
| 北海道 |
2 |
| 計 |
41 |
|
|
|
設 備
| 工場建坪 |
10,575坪 |
| 原動機 |
1,125馬力 |
| 主要機械 |
801台 |
|
|
|
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
戦後の復興 |
|
|
欧米先進国に並ぶために、国は軽工業を優先させて外貨を稼ぎ、近代化を図ることを推進した。
このような日常生活用品優遇の時代に鉛筆産業も恩恵を浴し、昭和22、23年には明らかな復興の兆しが見えてきた。
鉛筆生産用の資材については、指定生産資材配給制度による割当があり必要資材の入手が至難であった。
昭和21年度後半からは、主務官庁より業者に対し配給切符を交付する制度が実施されて、指定17品日中 鉛筆用資材として石炭、コークス、石油製品、鉄鋼二次製品、重要化学製品、油脂及油脂製品、ゴム、繊維製品、用紙、木材の資材が該当していた。 |
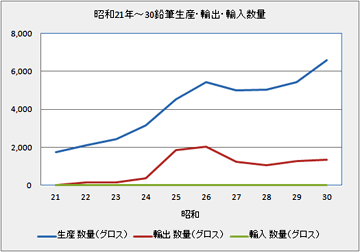 |
しかし、木材は原木として軸板製造業者に対して、統制の枠があり鉛筆材(軸板製品)となったものには、統制がなかった。建築制限その他木製品の制限があったために、当時は鉛筆材製造の新規業者が増加して、形ばかりの鉛筆軸板が、相当出回った。
鉛筆生産資材としての主要なものは、黒鉛、粘土、重油(シン原料)、木材、膠、糊料、塗料、金属粉(仕上原料)、板紙、印刷紙、糸(包装原料)等であるが、粘土と鉛筆軸板の他は、指定生産資材であった。
このため組合の役割は大きく、鉛筆の原材料購入資金を銀行より借入し組合員に貸付、板材の確保、主務官庁との連携、電力の供給要請、板材搬送の鉄道会社への要請など多岐にわたり奔走した。
昭和23年(1948)、「インセンスシダー需給協議会」を設置、鉛筆組合を介してインセンスシダーのプランクおよびスラットを共同購入し、業者の生産実績に基づいてこれを配分した。これによって開戦の昭和16年(1941)以来途絶していた良質な米国カリフォルニアのインセンスシダーの輸入が再開されることになった。
復興の実績は昭和24年対前年比130%、25年同143%という驚異的な勢いであった。
需給状況は、生産の増加と・価格の統制によって需給のバランスがとれていたが、24年後半ころから生産過剰の傾向がみえ、メーカーのなかには公定価格を割って乱売する業者もでてきた。
昭和15年以来実施されてきた鉛筆の公定価格は、昭和24年8月20日廃止されるに至った。
昭和24年度の企業数等を示すと、次の通りであるが、東京が中心地であって、企業形態も個人企業が59名、55%となり、従業員数も20人以下の企業者が約71%と中小企業が占めている。 |
|
地区別企業数および工場数
| 都道府県 |
企業数 |
工場数 |
都道府県 |
企業数 |
工場数 |
| 北海道 |
3 |
9 |
千葉 |
1 |
1 |
| 青森 |
1 |
1 |
東京 |
80 |
67 |
| 岩手 |
1 |
2 |
神奈川 |
0 |
1 |
| 山形 |
1 |
2 |
三重 |
1 |
1 |
| 長野 |
1 |
3 |
愛知 |
1 |
1 |
| 山梨 |
1 |
1 |
富山 |
1 |
1 |
| 群馬 |
2 |
3 |
岐阜 |
0 |
1 |
| 栃木 |
0 |
2 |
大阪 |
11 |
12 |
| 埼玉 |
4 |
5 |
兵庫 |
1 |
1 |
|
|
|
計 |
110 |
114 |
|
|
工程別・地区別企業数
| 工程作業 |
東京 |
大阪 |
その他 |
計 |
| 一貫作業 |
14 |
5 |
4 |
23 |
| 木工・塗・仕上作業 |
8 |
3 |
13 |
24 |
| 塗・仕上作業 |
47 |
0 |
0 |
47 |
| 芯専業 |
11 |
3 |
2 |
16 |
| 計 |
80 |
11 |
19 |
110 |
| 出典:文化用品工業便覧 |
|
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
大手企業6社、東京鉛筆工業協同組合から離れる
三菱鉛筆、トンボ鉛筆、ヨット鉛筆、コーリン鉛筆、地球鉛筆、森彌鉛筆 |
|
|
昭和22年(1947)12月、連合軍総指令部(GHQ)は、「過度経済力集中排除法」を交付した。企業間の支配関係を断つことに加えて、単独の巨大企業が持つ経済力の集中を排除することが目的だった。
昭和23年から公正取引委員会との調査、回答の再三にわたる経緯がみられる。
同法が組合に与えた影響に関する記録はないが、任意の日本鉛筆工業会を昭和23年6月1日に設立し東京鉛筆工業協同組合の上部団体として対応したと思われる。実質、昭和31年5月に制定されたJIS S 6001「鉛筆およびシン(輸出用)」規格の原案作成団体は日本鉛筆工業会となっている。
昭和26年4月12日開催の臨時総会において、数原三郎(三菱鉛筆)、小川八郎(トンボ鉛筆)、渡邉宏幸(ヨット鉛筆)各理事が辞任している。
大手6社は、昭和27年8月1日組合に再加入した。
公正取引委員会には同8月9日付け、三菱鉛筆、トンボ鉛筆、ヨット鉛筆の3社について
『1.国が鉛筆工業自体、国産業分野において占める位置が中小企業であり・・・・・。 2.業界は比較的狭小で当該3業者と本組合たる業者とは対立的な問題よりもむしろ共通的な問題につき相互に協調し合っていく必要のほうが多く、かつ実際的に官庁その他の連絡上においても組合加入を必要としている。 3.昭和27年7月9日の総会において業界協同強化のため本組合全員が希望と決議している』と加入を届出ている。
なお、コーリン鉛筆、地球鉛筆、森彌鉛筆の3社は、この期間に中小企業として認められたと思われる。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
JIS規格の制定とJISマーク表示の廃止 |
|
|
 |
技術的に進歩した製品、品質の水準を向上させるために、その規格化が重要視され、特に文部省において教育用品としての国内用鉛筆の規格の制定が要望され、また各関係方面よりの要望とともに鉛筆規格制定が急速化され本組合も協力し日本工業標準調査会日用品部会において検討審議した。 |
鉛筆規格の制定は、昭和24年12月第1回の規格原案作成委員会より昭和26年3月の官報告示までに専門の技術者の研究資料を基礎とし法令にもとづいて、学識経験者、生産者、販売者、消費者、官庁側より各委員が任命され本組合も参加、10数回にわたり審議の結果、科学的な検査方法を取り入れた規格「JIS Z 6605鉛筆(黒しん)」が昭和26年3月15日制定された。
規格の制定とともに品質管理の立場から工業標準化法第19条の指定品目として指定告示された。
制定とともにJIS生産技術審査要項並び品質管理等に関して説明会を開催し、JIS表示許可申請の促進を図った。その結果26年度中に、申請が約20名に及び半数が表示許可工場となった。
その後27年8社、28年2社、29年度2社が許可工場となりJISマーク普及率も急速に伸長していった。また昭和28年11月7日「JIS S 6002色鉛筆」が規格制定となり、昭和30年4月には8社が色鉛筆表示許可工場となり、日用品においては最も早い時期にJISが鉛筆に導入されることになった。
昭和28年11月には東京都通商産業局主催のJIS規格制定5周年記念行事、JIS宣伝隊街頭行進に参加するなど、平成10年まで長期にわたって鉛筆は、JISマーク表示普及率はほぼ90%となり、JISマーク商品の一般の普及に対しても非常に大きな貢献をした。
しかし、平成8年(1996)、行政改革と規制緩和の一端としてJISマーク表示制度の改革があげられた。組合はJIS表示許可工場(JIS部会)にアンケート調査を行い、存続について種々協議した結果、JIS規格は存続となり、JISマーク表示許可を返上することになった。平成10年(1998)3月20日までにJIS S 6005「鉛筆、色鉛筆及びシャープペンシルに用いるしん」表示許可工場8社、JIS S 6006「鉛筆及び色鉛筆」11社が許可証を返上した。
また、文具関係規格の消しゴム、シャープペンシル、スタンプ台、鉛筆削り器、朱肉、事務用のり、万年筆用ペン先、マーキングペン、ボールペン用中しん、電動鉛筆削り機、プラスチック字消し、水性ボールペン、水性ボールペン用中しん、絵具・クレヨン各規格も鉛筆規格と同様にJISマーク表示指定商品から削除された。
しかし、これにより大手スーパー、大手百貨店の店頭から中小メーカー生産の鉛筆が減少した。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
高度成長期の鉛筆産業 |
|
|
敗戦で約90万グロスにまで叩きのめされた鉛筆業界は昭和30年(1955)には、7倍強の660万グロスにまで復興した。
昭和31年の経済白書が「もはや戦後ではない」という言葉を残したことは有名で、産業史はこの昭和30年を境に「高度成長期」と呼ぶようになった。
昭和30年代には、わが国は復興期の「軽工業優先」を脱し、大規模な設備投資を伴う重化学工業が発展を始めた。こうした本格的な経済活動から多数の新製品が生まれ、それに伴って流通も大いに発展していった。 |
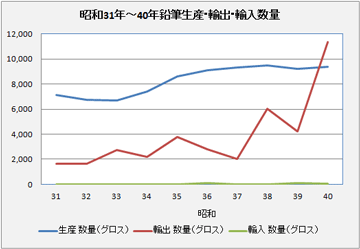 |
昭和30年度(1955)の事業報告書には「販売ルート別貢献度の内訳は、輸出30%、宣伝広告用等鉛筆50%、一般事務学習用10%他で占められていると推定する」と記録されている。
ここに消費財としての鉛筆を、「媒体」として利用活用させることで、鉛筆需要の据野をさらに広げた。無論、「宣伝広告用等鉛筆寄与度50%」の背景には、鉛筆仕上げ技術の大いなる進歩が裏付けられている。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
昭和41年(1966)生産量962万グロス(約14億本)のピークに達す |
|
|
新安保条約を推進する岸内閣と、この締結を阻止しようとする安保改正阻止国民会議が対峙し(60年安保)、代わった池田政権下では浅沼稲次郎社会党委員長が刺殺(1960年10月)されるという過激な事件が勃発、労使の対立が緊迫していた時代であった。この「浅沼事件」は小学校で「刃物を持たせぬ運動」に飛び火し、鉛筆削りをめぐって文具業界も緊急対応が迫られ、鉛筆製造業者が中心となって「鉛筆シャープナー工業会」を昭和35年(1960年)11月17日設立した。
米国ではJ.F.ケネディ政権が誕生(1961)、輸入超過に陥っていた米国は日本に対して「貿易の自由化(市場開放)」を迫ってきた。そうして昭和36年(1961)箱根で第1回「日米貿易経済合同委員会」が持たれることになり、わが国は「自由化」を受け入れ、この年、257品目の自由化が一気に決定した。 |
 |
鉛筆業界も「米国から著名鉛筆が参入してくる」とあって、技術改善等、さまざまな手立てを講じてこれに備えた。
緊迫した「自由化」の波であったが、むしろ、この間、わが国のGNPが前年比10%以上の伸びを示したことと、相呼応するように鉛筆製造業も急成長した時代であった。
昭和30年(1955)に生産数量600万グロス台にのせたわが国の鉛筆産業は昭和41年(1966)に962万グロスの頂きに立った。その躍進ぶりは「高度成長」をみごとに象徴している。
大手2社から通常価格の10倍という「高級鉛筆」が発売されたのも昭和41、42年である。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
ファンシー商品の誕生 |
|
|
前述の状況のとおり、鉛筆の生産に携わった企業が、昭和30年代にはもっとも多くなり、生産高も二桁の伸長を示している。大手企業は、国内需要向け生産に重点をおいて工場設備を増強し市場占有率を高めていった。
販売力の弱い中小企業は、問屋を通じて販売する企業、輸出を中心とする企業と大手の下請け生産を行う企業とに分化していった。
このため中小企業は、付加価値を高めた商品の開発に着手、文具総合メーカーから依頼された版権のキャラクターを印刷した鉛筆にヒントを得て、ダイヤ鉛筆、細軸鉛筆、金銀箔巻鉛筆、誕生石付鉛筆、香水入り鉛筆、ハート形、星形等々のファンシー商品の開発を行い、鉛筆の新しい商品分野で国内市場に参入し、それまで5円売りが主流であったものが倍の価格で販売できるようになり、業界の活性化に貢献した。
また、それまでの輸出鉛筆の市場は、東南アジア及び中近東地域といった発展途上国が中心で低価格であったが、アメリカ、ヨーロッパにも市場を拡大していき、30年代後半から40年代にかけて多くの中小企業が輸出貢献企業として通産省より認定されている。 |
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
製造技術の向上 |
|
|
1942年(昭和17年)アメリカでは1年に15億本の鉛筆が生産されていた。この当時、鉛筆の機械は普通ドイツでつくられていたが、ボストンで材木加工機械の製造をしていたS.A.ウッズ機械会社が刃のスピードを速くすることに成功、また、ドイツの機械は六角形の鉛筆を角と角をあうように切り出していたが、ウッズは切り口がそのまま面の部分になるような切り方に変えた。(ヘンリー・ペトロスキー著「鉛筆と人間」より)
わが国でも昭和30年代後半には、生産量の増加とともに製造工程における技術革新も大いに進んだ。塗装技術の向上、木工技術の進歩などであるが、木工技術では、当初、横六角で切削していた。
ドイツでは既に縦六角カットが普及されており、この木工機械を輸入、また、各社試行錯誤して木軸の成型段階で刃物の揺れを抑制することにより木軸の隙間を無くす切削が可能になるなど、木工工程の向上に取り組んだ。鉛筆の本数取りが横六角カットであったものが縦六角カットにより、7プライスラットから9本が確実に取れるようになり、生産性も向上し多大なコストダウンが図られた。 |
|
 |
横六角取り木軸の切削 |
|
|
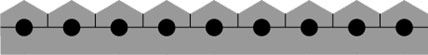 |
縦六角取り木軸の切削 |
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
筆記具の多様化 |
|
|
一方で、重苦しいベトナム戦争の長期化(1965〜1973)に伴う反戦運動の激化、公害問題の発生、そしてオイルショック(第1次石油危機/1973)と経済の拡大に伴うリスクも拡大していった時期であった。
昭和48年(1973年)までの鉛筆生産数量は年間800万グロス台の上限の位を確保していたが、同時にこの時代は本格的な筆記具の多様化が開花した時期でもあった。
昭和40年初期から50年中期にかけて、多様な筆記具が登場し、これが定着していく様子が雑貨統計年報の年別表に描かれている。 |
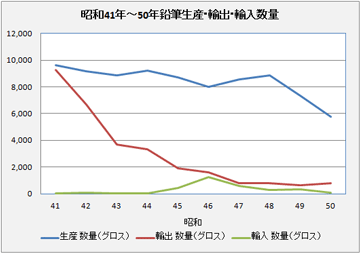 |
|
| 雑貨統計年報におけるそれぞれの初見は次のとおり。 |
|
| 統計報告が始まった年 |
| ボールペン |
昭和35年(1960) |
| マーキングペン |
昭和41年(1966) |
| シャープペンシル |
昭和44年(1969) |
|
|
|
| 昭和50年(1976年)代の鉛筆の生産は500万グロス台の高原状態を保ち、一方でシャープペンシル、ボールペン、電子文具等の次世代筆記具の生産は、一桁ずつ位を上げていった。「筆記具」の多様化と「筆記」の革新がこの年代に進んだのであった。 |
|
|
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
学童数の減少・キャラクター鉛筆 |
|
|
戦後のベビーブームにより、昭和33年の小学校児童数は、1,349万人であった。以降第2次ベビーブームがあったものの昭和62年には1,023万人、63年には987万人、平成4年には、895万人、平成9年には786万人、平成22年には699万人と減少傾向に歯止めがかからない状態となり、需要の核となる小学生の減少は鉛筆業界にとって厳しい状況となっている。
平成7年度の地場産業振興事業で小学生にアンケートを実施したが、小学校低学年では「漫画やキャラクターがついている鉛筆」「きれいな模様の鉛筆」を持っている割合が70%以上となっており、現在もキャラクター鉛筆が主流となっている。
平成6年(1994年)〜12年(2000年)鉛筆の生産は300万グロス台と昭和40年代の約3分の1に縮小を余儀なくされた。また、シャープペンシル、ボールペン、マーキングペン等の昭和40年代に花開いた多様な筆記具も内需においては爆発力を失っていった。それはマクロ経済の長期低迷、少子化、消費低減を促す地球環境保全運動等を如実に反映するものであった。
この少子化、消費低迷の時代にあって平成8年(1996年)、9年は鉛筆の生産が若干伸びている。これは学童文具メーカーによるアニメーション、テレビゲームなどの「漫画やキャラクターがついている鉛筆」、「ゲーム鉛筆」などメディアとタイアップした企画が小学生に受け入れられたことによるが、ブームは一時的であった。
以降、平成13年(2001年)〜19年(2007年)の国内生産は、200万グロス台に減少、大手企業が海外に生産拠点を移したこともあって平成18年(2006年)には国内生産と輸入数量が逆転し、平成20年(2008年)からは、100万グロス台となっている。 |
|
|
|
| ※ 統計資料は雑貨統計年表 |
| ※ 輸入は昭和63年からKgの統計に変更された。 |
| ※ 輸出は平成20年からKgの統計に変更された。 |
| ※ 6,000グロス≒5,400Kgで換算。 |
|
|
|
|
=目次に戻る= |
|
| |
|
|
|
結びに |
|
|
16世紀の鉛筆の始まりから21世紀の今日まで、鉛筆は教育、文化、産業の興隆と人類に欠かすことができない使命を担ってきた。
鉛筆は、幼児が文字を覚えるために、最初に使用する筆記具である。学童用筆記具として社会的な使命を果たしている。筆圧の強い人が使っても芯が折れにくく、また筆圧の弱い高齢者にも最適である。鉛筆の芯は、製作段階で1,000度から1,200度という高温で焼き固められる。そのため熱帯地域や、寒冷地域の過酷な状況な中にあっても問題なく書くことができる。鉛筆ほどいつでもさっと書けるという信頼性の高い筆記具はない。
主な材料の木材、黒鉛にしても天然の素材であり、「究極のエコ製品」ともいえる鉛筆は素晴らしい商品である。
わが国における国内生産は減少しているが、世界に目を向ければ、筆記具の中で最も多く生産されているのが鉛筆であり、発展途上国の識字率が高くなればなおのこと、今後の鉛筆市場の可能性は限りなく広がっていく。 |
|
|
| |
|
|
|
- TOPに戻る - |
|
|
|
|
|
C 2001 日本鉛筆工業協同組合,All right reserved. |
|